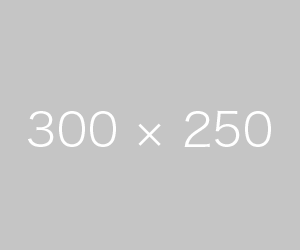かぜ症候群
かぜとは、自然に治癒する上気道のウイルス感染症のことです。上気道とは喉と鼻、肺の手前にある気管支といった空気の通り道のことを指します。かぜ症候群と呼称される場合もあります。
かぜを引き起こすウイルスが上気道各部位に感染することで炎症が起こり、鼻であれば鼻水、喉であれば喉の痛みや声枯れなど特有の症状が現れます。
かぜは、基本的には安静を保つことで自然回復する病気です。ウイルスに対する特効薬は存在しないため、解熱鎮痛剤や去痰剤など症状にあわせて対症療法を行うことが治療の基本となります
かぜの原因
かぜは、飛沫感染や接触感染によりウイルスが体内に侵入し増殖することで発症します。かぜを引き起こすウイルスとしては、ライノウイルス・コロナウイルス・RSウイルス・アデノウイルス・コクサッキーウイルス・エコーウイルス・パラインフルエンザウイルスなどがあります。
このように多くのウイルスがかぜの原因として知られていますが、もっとも頻度が高いのは「ライノウイルス」であり、およそ半分を占めています 。ライノウイルスに次いで多いのは「コロナウイルス」で、かぜの10~15%ほどを占めます。ライノウイルスは春と秋、コロナウイルスは冬に流行する傾向があり、通年性にかぜをひく機会があるともいえます。
RSウイルスやヒトメタニューモウイルスは鼻かぜの原因となる非常にありふれたウイルスですが、初めて感染したお子さんには症状がひどくなり入院が必要となることもあります。また初感染から時間が経った大人が子どもから感染することもあります。
急性咽頭炎、扁桃炎を合併する場合は溶連菌(A群β溶血性連鎖球菌)による細菌感染は重要で、血液検査を行い溶連菌感染が疑われる場合は抗菌薬の処方を行う場合があります。
治療方法
基本的には自然治癒が見込める疾患であり、また、ウイルスに対する特効薬も存在しません。そのため、治療の基本は対症療法になります。
溶連菌感染などの細菌性感染が疑われる場合は抗菌薬を処方することもあります。
基本的には診察時の症状に応じて、去痰剤、消炎鎮痛剤、吸入薬、アレルギー治療薬などを処方することが多いです。
院長からのお願い
誠に申し訳ないことですが、発熱外来診療は、かかりつけの患者さんに限定しております。
また受診前に必ず電話連絡をお願いします。
初診で発熱外来を受診したい方は、まずご自身で「研究用ではない新型コロナ抗原検査キット」で検査陰性を確認してから、受診が可能か電話連絡をして下さい。詳しくは発熱外来のリンクを確認して下さい。
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の位置付けは「5類感染症」に変更となりました。
当院でもかかりつけ患者さんを含めて可能な限り、上記のごとくOTC薬となった抗原検査キットを用いて事前にコロナ検査を行っていただくよう、電話で相談を受けた際にお願いしております。そのような対応が困難な患者さんには、原則クリニックの駐車場内での検査をお願いする場合もあります。クリニックのスペース的に完全に玄関から発熱患者さんの動線を分けることができないためです。
当院には
- 免疫抑制剤を使用している患者さん
- 肺気腫や気管支喘息の患者さん
- 85歳以上で要介護状態の患者さん など
新型コロナウイルス感染すると重篤化する可能性のある慢性疾患で通院されている患者さんがたくさんおられます。
現在、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に変更約1ヶ月が経過しましたが、当院の規模や専門性および社会的な状況を鑑みると、初診の発熱外来を行うだけの余裕はなく、かかりつけ患者さんの治療をまずしっかりと行なってゆきたいと思っています。
ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2023年6月2日
新潟三条ささき内科・消化器内科クリニック
院長 佐々木一之